【受験ハック06】受験科目分析<英語><社会>
無料体験(1週間)へのご参加は、お気軽に教室までご連絡ください


TEL:070-5412-2112 【アサノジュク学習相談室】
受験生必見
 あなたにオススメの県立高校をスグに診断
あなたにオススメの県立高校をスグに診断

【 高校ドコ行く?シミュレーター ドコ高?@Okinawa 】
Instagaramでは授業風景やイベントの様子をお伝えしています

ぜひフォローよろしくお願いします

【アサノジュク インスタグラムページ】
アサノジュクのFacebookページが出来ました

「いいね!」を押していただくと、新着情報がタイムラインに表示されるようになります

【アサノジュク フェイスブックページ】
アサノジュクのTwitterアカウントが出来ました

フォローいただくと、新着情報が素早くご覧いただけます

【アサノジュク Twitterアカウント】
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
みなさん、こんにちわ。アサノジュク塾長の浅野です。
本日で第6回目となりました。
過去5回の記事は下記のリンクからご覧いただけます。
【受験ハック05】受験科目分析<国語><理科>
http://asanotaiki.ti-da.net/e10560956.html
【受験ハック04】合格までの道のり解析(卒業生編)
http://asanotaiki.ti-da.net/e10533661.html
【受験ハック03】各高校の情報を手に入れよう
http://asanotaiki.ti-da.net/e10517461.html
【受験ハック02】志望校の選び方
http://asanotaiki.ti-da.net/e10504028.html
【受験ハック01】沖縄の高校入試について
http://asanotaiki.ti-da.net/e10491349.html
本日は【受験ハック06】受験科目分析<英語><社会>をお送り致します。

【受験ハック06】受験科目分析<英語><社会>
試験を行う順序は前回の記事にてご説明致しました。
英語は初日最終科目、社会は2日目の最初の科目に当たります。
それぞれの注意ポイント・対策方法を順にお伝えします。
まずは英語から。
◆ 選択問題が豊富な科目
他の4科目と比較して、英語の試験に違いがあるポイントは選択問題(4択)の豊富さです。
実際に問題と解くことで体感できますが、スペルやアルファベットを書き込む問題は多くありません。
もちろん、選択問題であろうが、準備は入念に必要です。
しかし、ランダムに解答を書き込んでも、10点程度の点数が見込めるのも、また事実です。
選択問題が多いからこそ、念入りに準備すべき点をいっしょに考えていきましょう。
◆ 聞き取り&読み取りの技能が重要
一般的に英語の技能は4技能(読み取り、書き取り、聞き取り、発音)と呼ばれますが、
沖縄県の高校入試ではそのうち2技能(読み取り、聞き取り)が重要視されています。
問題構成としては大問11までのうち、1~3は聞き取り(リスニング)4~7が文法問題(読み取り)
8~10が長文読解(読み取り)、11が英作文(書き取り)です。
近年は英作文問題に趣向を凝らしすことが多くなり、難易度が増しています。
しかし、配点としては全体の10%程度で、残り90%は読み取り・聞き取りに重心があります。
読み取り・聞き取りの内訳は、読み取りが65%、書き取りが25%程度です。
英検3級以上に見られる、発音に関する面談形式のテストはありません。
また、定期テストでよく見られるアクセントに関する問題も過去数年出題されていません。
◆ まずは単語を"読める"こと。
中学校3年間の間で1500以上の英単語を理解する必要があります。
まずはそれらを"読める"ことが最優先事項だと、僕は考えています。
ここでの"読める"には2つの意味があります。
1つは発音がわかること(appleをアップルと読めること)です。
たどたどしい発音でも問題なしです。
周囲には英語の勉強が特段に進んでいる友人らがいるかもしれません。
(英会話教室に通っている生徒など)
高校入試では、それほどの技能は求められていませんので、ご安心くださいね。
2つ目は日本語訳を理解していることです。
日本語訳は1つとは限りません。同じ単語に2つ以上の意味がある場合もあります。
1つでも多く理解している方が、もちろん受験には有利ですから、覚える努力を続けましょう。
「英語って、何から勉強すればいいの?」
と悩ましい生徒は、まずは単語が読めることに注力してみましょう。
続いて社会の解説です。
◆ 社会の出題は3等分
中学校で学ぶ社会は大きく3つの分野に別れています。
それぞれ地理・歴史・公民です。
高校入試の問題は、7つの大問から構成されており、
地理が2問、歴史が2問、公民が2問、総合問題(沖縄特有)が1問と固定されています。
この中で最も得点しやすい単元は、公民です。
中3の夏頃から始まる新しい単元、公民。
教科書範囲の履修は12月頃で終わっている学校が多いでしょう。
全体の3分の1を占める公民単元ですが、学習期間は5ヶ月程度で、
他の2単元に比べ短く、情報量も少ないと言えます。
社会が苦手という生徒こそ、新しく取り組む公民で挽回することが、入試攻略の鍵となります。
なお、地理は世界地理・日本地理に分別され、歴史は江戸時代までと江戸時代以降に分けられます。
公民は政治分野と経済分野に分けられ、それぞれから大問1つ分の出題がされることも理解しておきましょう。
◆ 歴史の勉強にはコツがある!
定期テストで歴史の単元が出題されるときは、教科書○ページから○ページまでというように範囲が指定されます。
すなわち、室町時代のテストだとか、江戸時代のテストだとか、そういう区分になります。
しかし、入試ではもちろん全範囲(全年代)が出題されますから、定期テストと同じ様に対策することは出来ません。
また、出題を紐解くと、年代を超えた"比較"が多く出題されます。
年代(時代)ごとの覚え方を続けると、年代を超えた"比較"の問題に対応できません。
そこで、受験に向けては、3つ縦軸で歴史を理解することを意識しましょう。
(年代ごとに切り分けて理解することは、横軸で分けて理解する方法です。)
1つめの軸は"政治"です。天皇から将軍へなど政治の中心の移り変わりやその背景を理解しましょう。
2つめの軸は"文化"です。中学校で学ぶ文化は飛鳥(あすか)文化に始まり、派手な文化と質素な文化の交互で繰り返されています。その順序と内容を理解しましょう。
3つめの軸は"海外"です。海外で一括りにすることは乱暴な気もしますが、中学校の歴史で学ぶ海外事情は多くありません。隋との外交にはじまり、近代のアメリカ経済の発展まで海外と日本の比較・関わりが続きます。それらを時系列で理解する必要があります。
この3つの軸を1つずつ、昔から近代に向けて理解できれば、歴史への対応は慣れることができます。
◆ 図表の読み取りがキモ
地理は記憶に頼る対策が最も難しい単元であり、あなどれない単元です。
社会は中1のはじめに地理から始まったことが原因か、地理はできると勘違いを起こすことがあります。
しかし、入試の地理は記憶(知識)だけでは対応できない図表問題が多く出題される傾向があります。
帯グラフや雨温図、地形図など、与えられた資料を正確に読み解き、求められる解答を書き込む力が必要です。
そのためには、まずは図表に見慣れることから始めましょう。
図表に特化したワークを解くもよし、実際に過去問に触れるもよしです。
決して「できるだろう」と油断せず、余裕を持って、落ち着いて準備してくださいね。
◆ 最後に
英語と社会は比較的高得点が安定して取れる科目です。
得意な生徒らはもちろん、苦手な生徒こそ、目標点(合格基準点)に必ずタッチできるよう準備が必要です。
入試の鉄則の1つ、"得点しやすいところから取る"を徹底して、英語なら単語の理解から、
社会なら公民の理解から、順に理解を深めて行きましょう。
素晴らしい受験準備ができることを祈っています。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
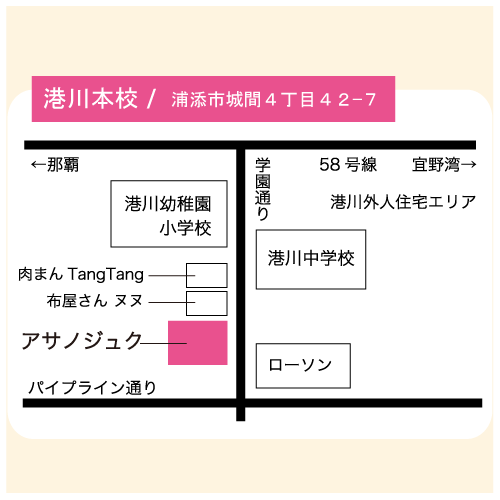

アサノジュクへのお問い合わせ、ご質問、講話依頼等のご連絡は、
(電話) 070-5412-2112
(メール) asanotaiki@asanojuku.com
中学生,小学生,学習塾,高校入試,受験




